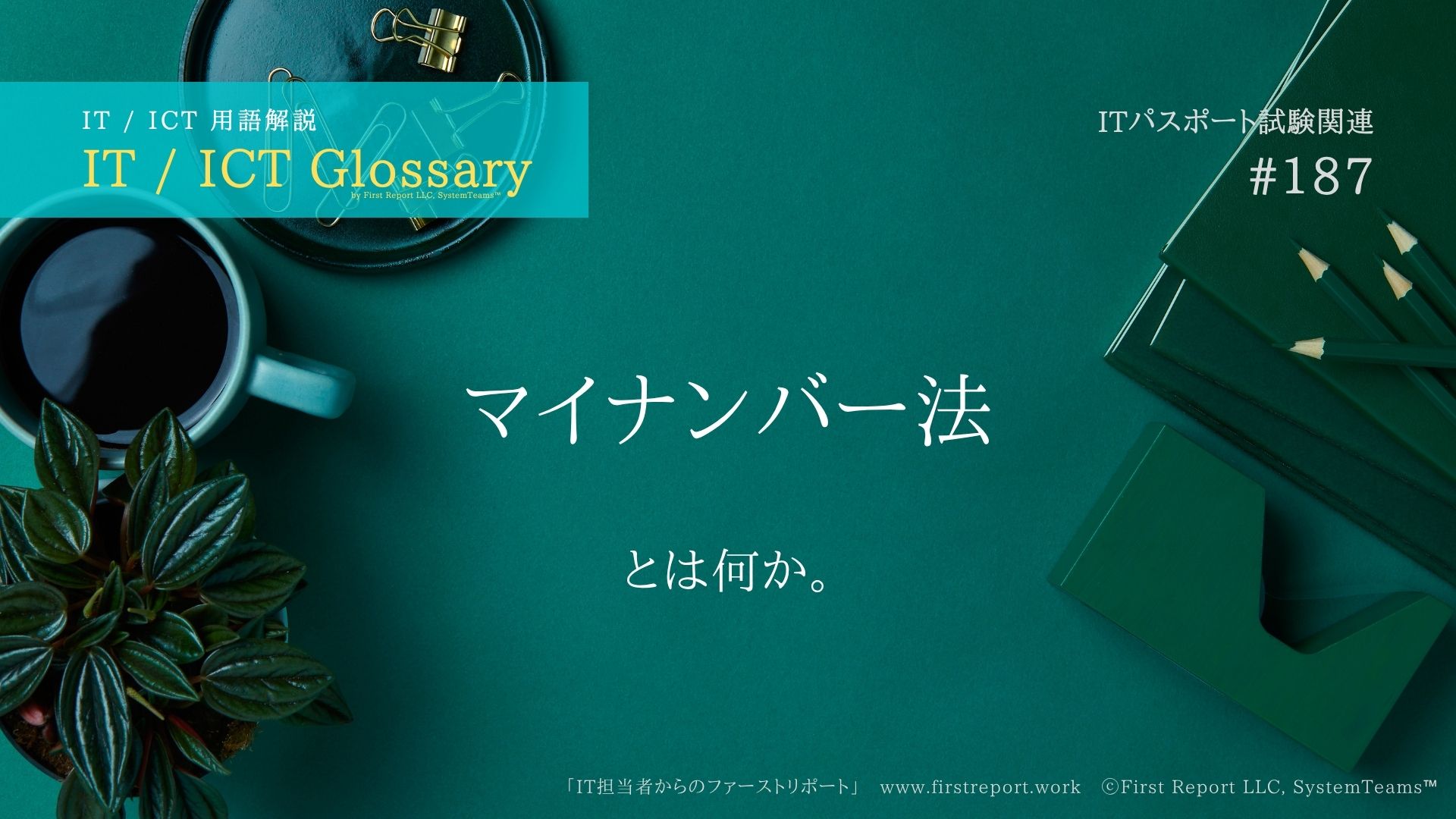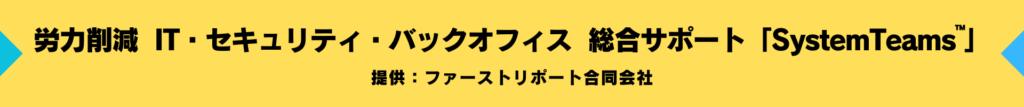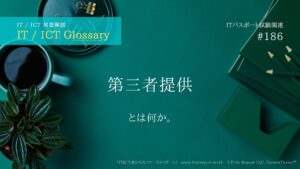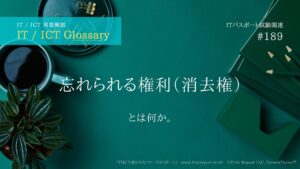「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「マイナンバー法(番号利用法)」です。
大まかに説明すると
「マイナンバー法(番号利用法)」は、マイナンバー(個人番号)の取扱いを定めた法律です。
これは、一般的な「個人情報保護法」に対する「特別法」と位置づけられ、個人情報保護法よりも厳しいルールが優先して適用されます。
最大のポイントは、マイナンバーの利用目的が、法律によって「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に厳格に限定されている点です。
これ以外の目的(例:会員番号としての利用)でマイナンバーを収集・利用することは固く禁止されており、違反した場合の罰則も非常に重く設定されています。
はじめに
今回は、「個人情報保護法」よりも、さらに厳しく特定の情報を守る法律、「マイナンバー法」について解説します。
厳格さが問われる重要な法律です。
マイナンバー法とは?
「マイナンバー法」とは、通称です。
正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と言い、「番号利用法」とも呼ばれます。
この法律は、日本に住民票を持つすべての人(外国人含む)に割り当てられた12桁の「マイナンバー(個人番号)」の取り扱いに関するルールを定めたものです。
マイナンバー法の目的
なぜマイナンバー制度が導入されたのでしょうか?
目的は大きく3つあります。
【最重要】個人情報保護法との「違い」
マイナンバー(個人番号)は、「個人識別符号」であり、当然「個人情報」です。
そのため、マイナンバー法は「個人情報保護法」の「特別法」という位置づけになります。
「特別法」とは、ある特定の分野において、一般的な法律(一般法)よりも優先して適用される、より厳しい、または詳細なルールのことです。
つまり、マイナンバーの取扱いに関しては、個人情報保護法よりも、マイナンバー法という特別な厳しいルールが優先されるのです。
マイナンバー法の「厳しいルール」
マイナンバー法が個人情報保護法と比べて「いかに厳しいか」を3つのポイントで押さえましょう。
利用目的が「超限定」されている
個人情報保護法では、利用目的は事業者が決め、本人に通知すれば良い、と比較的柔軟でした。
しかし、マイナンバー法では、マイナンバーを利用できる目的(事務)が、法律で「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に厳格に限定されています。
例えば、アルバイト先があなたのマイナンバーを求めるのは、「税金(源泉徴収)」や「社会保障(雇用保険)」の手続きに使うためです。
それ以外の目的、例えば「社員番号の代わりに使う」「ポイントカードの会員番号にする」といった目的でマイナンバーを利用することは、固く禁止されています。
収集・提供の制限が「超厳しい」
上記3分野の目的が「ある」場合でなければ、他人(会社、役所など)にマイナンバーを提供する(教える)ことはできません。
逆に、会社側も、上記3分野の目的が「ない」のに、従業員や顧客にマイナンバーの提供を求めてはいけません。
例:レンタルビデオ店が、本人確認のために「マイナンバーカードの裏面(マイナンバーが記載された面)をコピーさせてください」と要求するのは、法律違反です。
罰則が「超重い」
マイナンバー法は、個人情報保護法と比べても、違反した場合の罰則(懲役や罰金)が非常に重く設定されています。
例えば、他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく他人に提供したりすると、重い刑事罰が科されます。
これは、マイナンバーが国の行政基盤に関わる、最も重要な個人情報の一つだからです。
まとめ
「マイナンバー法(番号利用法)」は、マイナンバー(個人番号)の取扱いを定めた法律です。
これは「個人情報保護法」の「特別法」にあたり、より厳格なルールが優先されます。
最大のポイントは、利用目的が「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に限定されている点です。
これ以外の目的でマイナンバーを集めたり、利用したりすることは固く禁止されており、罰則も非常に重いことを覚えておきましょう。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類2「法務」
5. セキュリティ関連法規
目標「代表的なセキュリティ関連法規の概要を理解する。」
説明1「我が国のサイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項等を定めたサイバーセキュリティ基本法があることを知り、その概要を理解する。」
説明2「実際に被害がなくても罰することができる、不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)があることを知り、その概要を理解する。」
説明3「パーソナルデータ、個人情報、個人データの違いを理解する。」
説明4「その他、情報セキュリティに関連する各種法律の概要を理解する。」
(3) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
- 保護の対象となる個人情報、適用される事業者、義務規定など。
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。