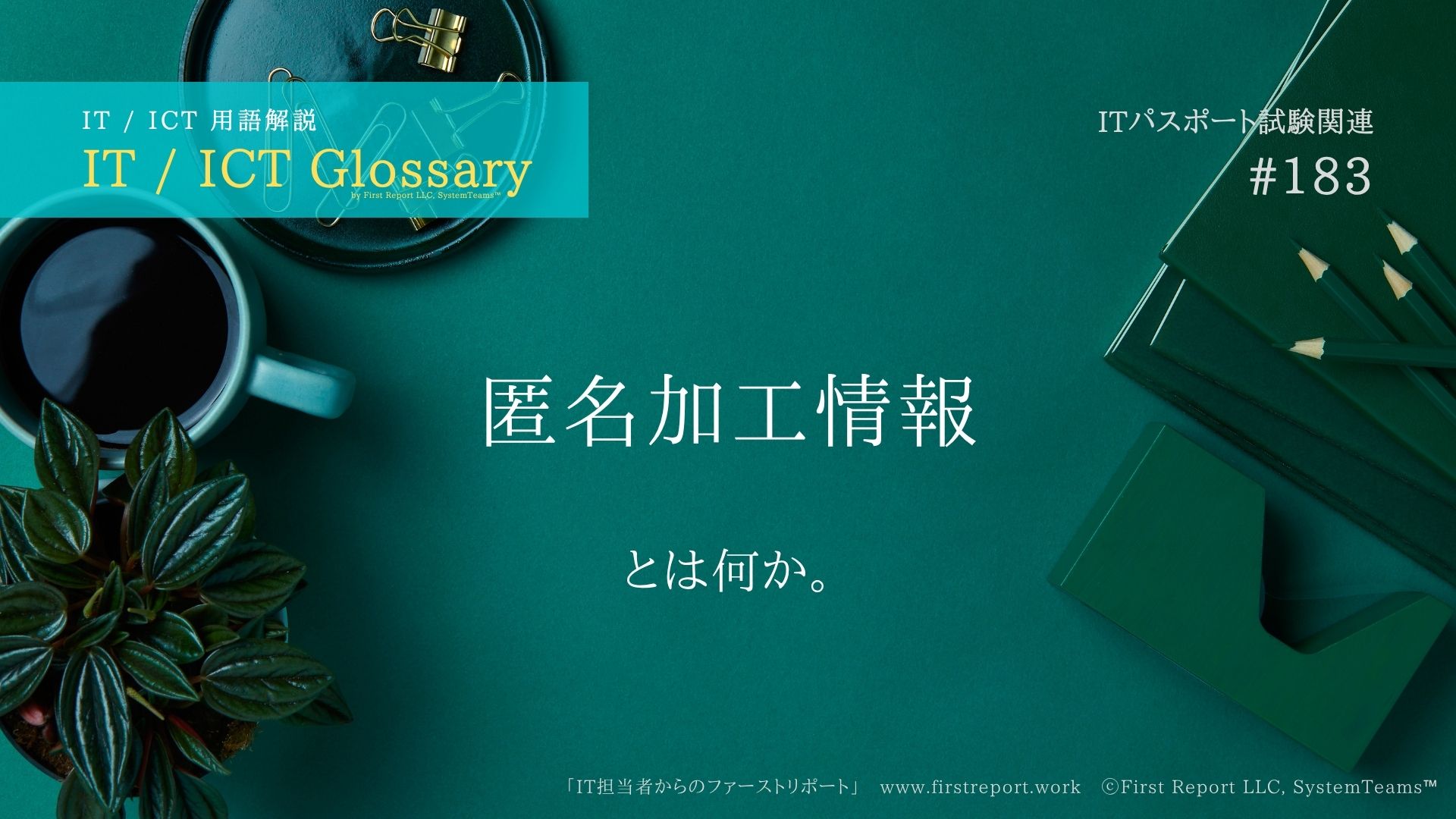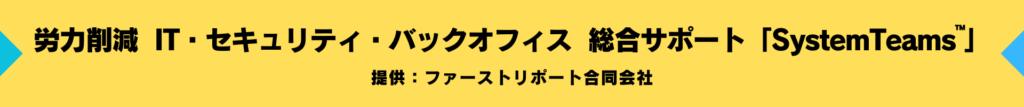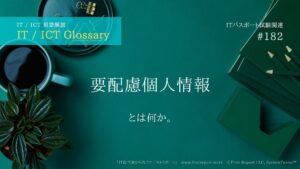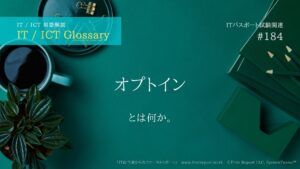「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「匿名加工情報」です。
大まかに説明すると
「匿名加工情報」とは、個人情報を、特定の個人が識別できず、かつ元の情報に復元できないように加工した情報のことです。
例えば、氏名を削除し、住所を「〇〇県」までに丸めるなどの処理をします。
個人情報保護法では、この「匿名加工情報」にすれば、もはや「個人情報」とは扱われません。
最大のメリットは、事業者がこの情報を作成・利用する際、「本人の同意」なしに、データの分析や第三者への提供(販売など)が可能になる点です。
これは、個人のプライバシーを守りつつ、ビッグデータなどの「利活用」を促進するための仕組みです。
はじめに
今回は、「個人情報保護法」の「保護」と「利活用(ビジネスでの活用)」のバランスをとる上で、非常に重要なカギとなる「匿名加工情報」について解説します。
ビッグデータを活用したい企業と、プライバシーを守りたい個人。その両方を実現するための仕組みです。
匿名加工情報とは?
「匿名加工情報」とは、個人情報を「特定の個人を識別できない」ように加工し、かつ、その個人情報を「元に戻す(復元)ことができない」ようにした情報のことです。
例えば、以下のような加工を行います。
- 名前:「Aさん」「Bさん」のように、特定の個人が分からない記号に置き換える(または削除する)。
- 生年月日:「1990年4月1日生まれ」を「1990年代生まれ」や「30代」のように丸める。
- 住所:「東京都新宿区〇〇」を「東京都」のように、詳細な情報を削除する。
このように加工することで、「〇〇さん」という個人は特定できなくなるけれど、「東京都に住む30代の人が、この商品をよく買っている」といった統計的な分析や、新しいサービスの開発には役立つデータとして活用できるようになります。
なぜこの仕組みが必要なの?(匿名加工情報のメリット)
企業は、顧客の購買履歴や行動履歴といった「ビッグデータ」を分析して、より良い商品やサービスを生み出したいと考えています。
しかし、そのデータが「個人情報」のままだと、分析に使うにも、他の会社と共同で研究する(第三者提供する)にも、原則として一人ひとりの「本人の同意」が必要になり、非常に手間がかかります。
そこで「個人情報保護法」では、決められたルールに従って「匿名加工情報」にさえしてしまえば、それはもはや「個人情報」とは扱われず、 「本人の同意」がなくても、自由に分析したり、第三者に提供(販売など)したりできる というルールを設けました。
これが、事業者(企業)にとっての最大のメリットです。
個人のプライバシー(匿名性)は守りつつ、データの「利活用」を促進するための仕組みなのです。
【重要】匿名加工情報のルール
ただし、何でも自由に加工して良いわけではありません。
事業者が「匿名加工情報」を作成・利用する際には、厳しいルールが定められています。
適切な加工
個人情報保護委員会の定める基準に従って、個人を特定できる情報(名前など)を削除したり、置き換えたりしなければなりません。
「元に戻せない」こと
加工した情報を、元の個人情報と照合して「このデータは〇〇さんのものだ」と特定(復元)しようとする行為は、固く禁止されています。
公表義務
匿名加工情報を作成したときや、第三者に提供するときは、「どのような項目(例:年齢、購買履歴)を含んでいるか」をインターネットなどで公表しなければなりません。
「仮名加工情報」との違い(参考)
最近の法改正で、「仮名加工情報」という似た言葉も登場しました。
- 匿名加工情報:
- 目的:第三者提供や、利用目的の制限なく分析できる。
- 加工レベル:元に戻せないようにする。
- 扱い:もはや「個人情報」ではない。
- 仮名加工情報:
- 目的:社内での分析に限定して利用する。
- 加工レベル:他の情報と照合すれば、元に戻せる(復元できる)。
- 扱い:「個人情報」の一種として、引き続き一定の管理が必要。
まず「匿名加工情報 = 元に戻せない = 本人同意なしで第三者提供OK」という組み合わせをしっかり覚えてください。
まとめ
「匿名加工情報」とは、個人情報を「個人が特定できない」かつ「元に戻せない」ように加工したデータです。
この情報にすることで、事業者は「本人の同意」なしにデータを分析したり、第三者に提供したりすることが可能になります。
これは、個人のプライバシー保護と、データの利活用(ビッグデータビジネス)を両立させるための重要な仕組みです。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類2「法務」
5. セキュリティ関連法規
目標「代表的なセキュリティ関連法規の概要を理解する。」
説明1「我が国のサイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項等を定めたサイバーセキュリティ基本法があることを知り、その概要を理解する。」
説明2「実際に被害がなくても罰することができる、不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)があることを知り、その概要を理解する。」
説明3「パーソナルデータ、個人情報、個人データの違いを理解する。」
説明4「その他、情報セキュリティに関連する各種法律の概要を理解する。」
(3) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
- 保護の対象となる個人情報、適用される事業者、義務規定など。
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。