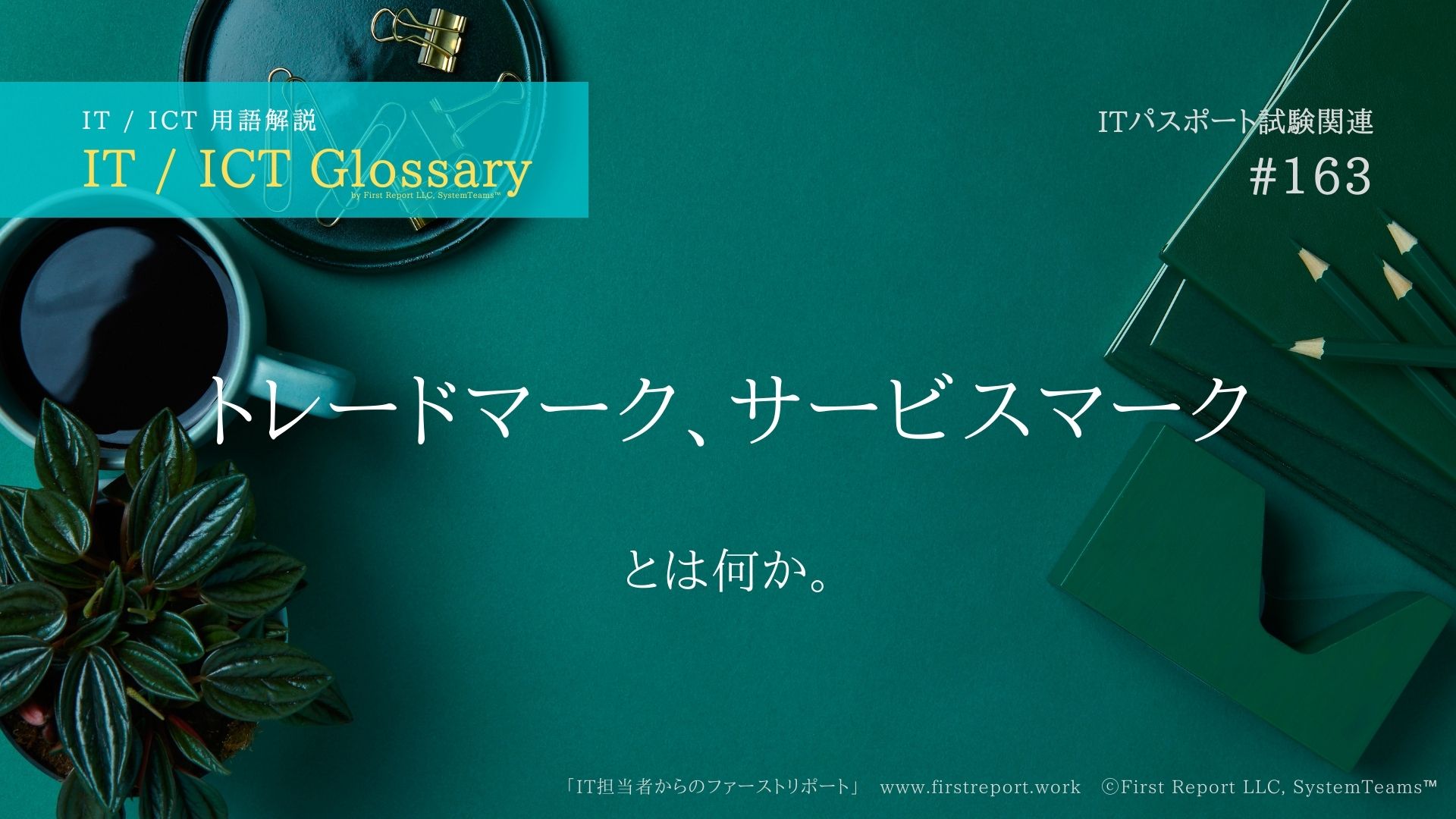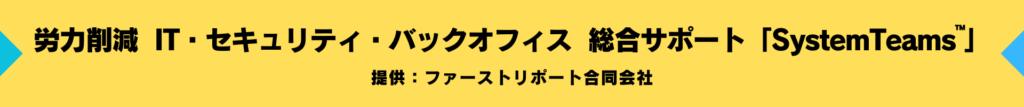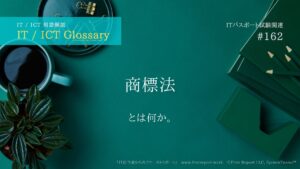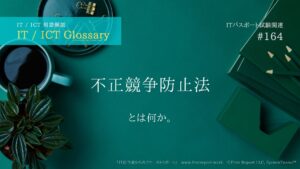「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「トレードマーク、サービスマーク」です。
大まかに説明すると
トレードマークとサービスマークは、どちらも「商標」の一種です。
一般的に、これらを総称して「商標」と呼びます。
両者の違いは、マークを何に付けるかにあります。「トレードマーク」は、自動車やジュースといった有形の「商品(Trade)」に付けるマークを指します。
一方、「サービスマーク」は、銀行や運送、インターネット通信といった無形の「役務(Service)」に付けるマークを指します。
日本の商標法では両者を区別せず「商標」として扱いますが、その対象には商品とサービスの両方が含まれると理解することが重要です。
はじめに
お店で商品を見ていると、®や™といった小さな記号が、ロゴマークの近くに付いているのを見たことはありませんか?
これらは商標に関連する記号ですが、その中でも「トレードマーク」や「サービスマーク」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
どちらも「商標」を指す言葉ですが、厳密には少し違いがあります。
ITパスポートの学習においても、この違いを理解しておくと、商標法の理解がより深まります。
今回は、この2つのマークの違いについて、分かりやすく解説します。
結論:マークを付ける対象が違う!
結論から言うと、トレードマークとサービスマークの違いは、「マークを何に対して使用するか」という点にあります。
トレードマーク (Trade Mark)
- 対象: 商品 (Goods)
- 意味: 「Trade = 取引、商業」の名の通り、形のある「モノ」、つまり商品に付けられるマークです。
- 具体例:
- 自動車のエンブレム
- お菓子のパッケージに印刷されたブランド名
スマートフォンの背面にあるロゴ
サービスマーク (Service Mark)
- 対象: 役務 (Services)
- 意味: 「Service = 奉仕、業務」の名の通り、形のない「サービス」に付けられるマークです。「役務(えきむ)」とは、法律用語でサービスのことだと考えてください。
- 具体例:
- 銀行や保険会社のロゴ
- 運送会社のトラックに描かれたマーク
- 携帯電話会社の通信サービスの名前
- オンラインゲームのタイトルロゴ
簡単に言えば、「モノにつけるのがトレードマーク、サービスにつけるのがサービスマーク」と覚えると良いでしょう。
日本の法律ではどうなっている?
ここで一つポイントがあります。アメリカなど一部の国では、法律上「トレードマーク」と「サービスマーク」を区別して扱っています。
しかし、日本の商標法では、この2つを区別していません。 日本の法律では、サービスマークもすべて含めて「商標」という一つの言葉で定義しています。
商標法の条文を見ても、「商品の商標」と「役務(サービス)の商標」が保護対象であると書かれており、両者をまとめて扱っていることが分かります。
ですから、ITパスポート試験対策としては、「日本の法律上はどちらも『商標』として保護される」と理解しておけば十分です。
ただし、その「商標」という大きな枠組みの中に、商品に関するもの(トレードマーク)と、サービスに関するもの(サービスマーク)の2種類がある、という内訳を知っておくと、より正確な知識になります。
なぜIT分野でこの区別が役立つのか?
現代のITビジネスは、「モノ」の販売だけでなく、「サービス」の提供が中心になっています。
- ソフトウェアをCD-ROMで販売する → 商品なので、そのパッケージのロゴはトレードマーク
- ソフトウェアを月額課金で提供する(SaaS) → サービスなので、そのサービスのロゴはサービスマーク
- オンラインストレージサービス → サービスなのでサービスマーク
- SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス) → サービスなのでサービスマーク
このように、IT業界では形のない「サービス」が非常に多いため、サービスマークの重要性が高まっています。
トレードマークとサービスマークの違いを意識することで、ある企業が提供しているものが「製品」なのか「サービス」なのかを、より明確に捉えることができるようになります。
まとめ
トレードマークは「商品」に、サービスマークは「サービス(役務)」に付けられるマークです。
この2つは、マークを付ける対象が違うだけで、どちらも企業のブランドや信用を守るための大切な目印です。
日本の法律では両者を区別せず、まとめて「商標」として保護しています。
ITパスポートの学習では、この基本的な違いと、日本の法律での扱い方をセットで覚えておきましょう。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類2「法務」
4. 知的財産権
目標「知的財産権にはどのような種類があり、何が法律で守られ、どのような行為が違法
に当たるのかの基本を理解する。」
説明「コンピュータプログラムや音楽、映像などの知的創作物に関する権利は、法律で守
られていることを理解する。」
(2) 産業財産権関連法規
- 発明やデザインなどを登録することによって守られる権利があること
- 無断使用は違法であること
- AI が学習に利用するデータ、AI が生成したデータについて、それぞれ産業財産権の観点で留意する必要があること
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。