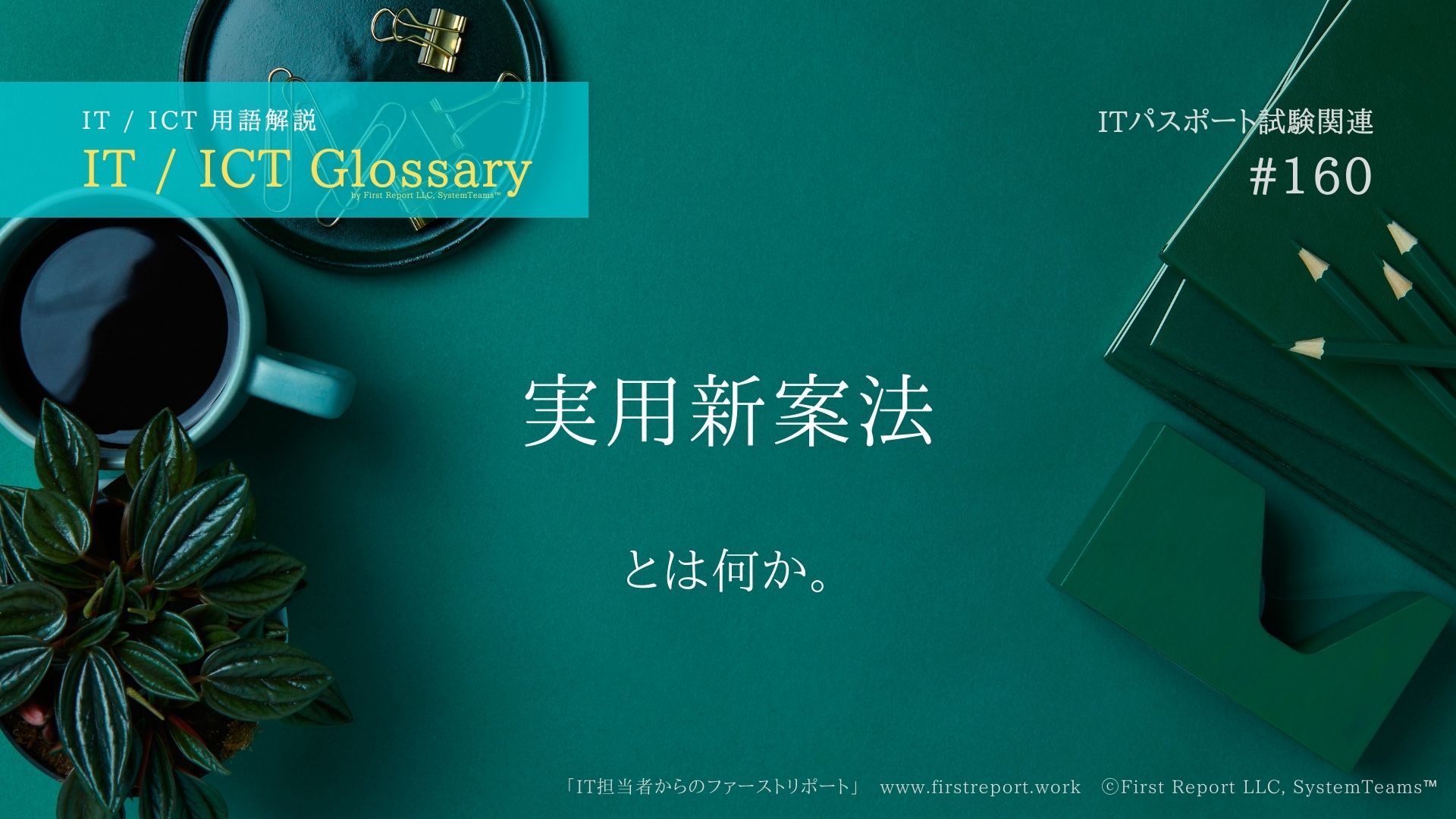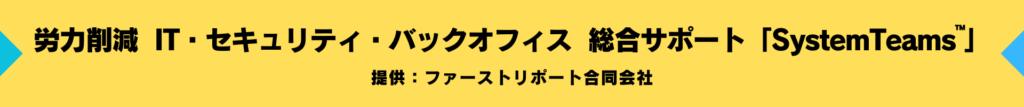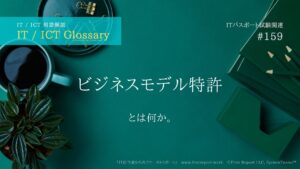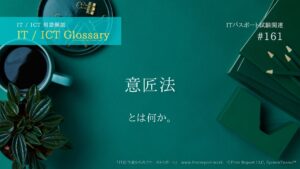「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「実用新案法」です。
大まかに説明すると
実用新案法(じつようしんあんほう)は、物品の形状や構造に関する、ちょっとした工夫やアイデアである「考案」を保護するための法律です。
特許法が保護する「高度な発明」に対し、実用新案法は「小発明」とも言えるような、より身近なアイデアを対象とします。
例えば「消しゴム付き鉛筆」のようなものが典型例です。審査が早く、費用も安いというメリットがありますが、保護される期間は出願から10年と特許より短くなっています。
技術的なレベルは高くなくても、便利な日用品などを守るのに役立つ法律です。
はじめに
周りにある文房具や日用品を思い浮かべてみてください。
「このペン、すごく持ちやすいな」「このファイル、書類が探しやすいように工夫されているな」と感じたことはありませんか?
こうした、日々の生活を少し便利にする「ちょっとした工夫」。
このような「小発明」とも言えるアイデアを保護するのが「実用新案法(じつようしんあんほう)」です。
今回は、特許法としばしば比較される実用新案法について、その特徴と違いを分かりやすく解説していきます。
実用新案法とは?
実用新案法は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を保護する法律です。
ここで重要なのは、保護対象が「考案」であること、そしてそれが「物品」に関するものに限定されている点です。
考案(こうあん)
特許法でいう「発明」ほど高度なものでなくてもよい、技術的なアイデアを指します。そのため、実用新案は「小発明」と呼ばれることもあります。
物品の形状、構造又は組合せ
保護されるのは、目に見える「モノ」に関する工夫だけです。例えば、新しい物質の作り方や、ソフトウェアのアルゴリズムのような「方法」は対象外となります。
具体例:
- 形状の考案: 持ちやすいように工夫されたグリップの形
- 構造の考案: 芯が折れにくいシャープペンシルの内部構造
- 組合せの考案: 消しゴムと鉛筆を一体化させた「消しゴム付き鉛筆」
特許法との違い
実用新案法を理解する上で最も重要なのが、特許法との違いです。ITパスポート試験でも、この比較は頻出ポイントです。
| 項目 | 特許法 | 実用新案法 |
|---|---|---|
| 保護対象 | 発明(技術全般) | 考案(物品の形状・構造・組合せ) |
| 技術レベル | 高度なもの | 高度でなくてもOK |
| 審査 | 実体審査あり(厳しい審査) | 無審査主義(方式審査のみで登録) |
| 保護期間 | 出願から20年 | 出願から10年 |
| 権利行使 | 登録後すぐに可能 | 「技術評価書」の提示が必要 |
最大のポイントは「審査」の方法です。
特許は、その発明が本当に新しいか、優れているかを審査官が厳しくチェックする「実体審査」があります。
これには時間も費用もかかります。
一方、実用新案は、書類の形式さえ整っていれば、中身のレベルを問われずに登録される「無審査主義」をとっています。
そのため、スピーディーかつ安価に権利を取得できるのが大きなメリットです。
ただし、権利の力は特許権に比べて少し弱く、他人に権利を主張する際には、まず特許庁に「この考案は本当に価値がありますか?」という評価書(技術評価書)を作成してもらう必要があります。
IT分野と実用新案法
実用新案法は、ソフトウェアのような「方法」の発明は保護対象外なので、IT分野との直接的な関わりは特許法ほど多くありません。
しかし、例えば「スマートフォンを立てかけられる便利なケース」や「ケーブルをすっきりまとめるための機器の構造」といった、IT機器のアクセサリーや周辺機器に関する物理的な工夫は、実用新案の対象となり得ます。
まとめ
実用新案法は、物品に関する「ちょっとした工夫(考案)」を、早く、安く保護するための法律です。
特許法との違い、特に「保護対象が物品限定」「無審査主義」「保護期間が10年」という3つのポイントをしっかり押さえておきましょう。
私たちの身の回りにある便利なグッズの多くは、こうした実用新案の仕組みによって守られているのかもしれませんね。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類2「法務」
4. 知的財産権
目標「知的財産権にはどのような種類があり、何が法律で守られ、どのような行為が違法
に当たるのかの基本を理解する。」
説明「コンピュータプログラムや音楽、映像などの知的創作物に関する権利は、法律で守
られていることを理解する。」
(2) 産業財産権関連法規
- 発明やデザインなどを登録することによって守られる権利があること
- 無断使用は違法であること
- AI が学習に利用するデータ、AI が生成したデータについて、それぞれ産業財産権の観点で留意する必要があること
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。