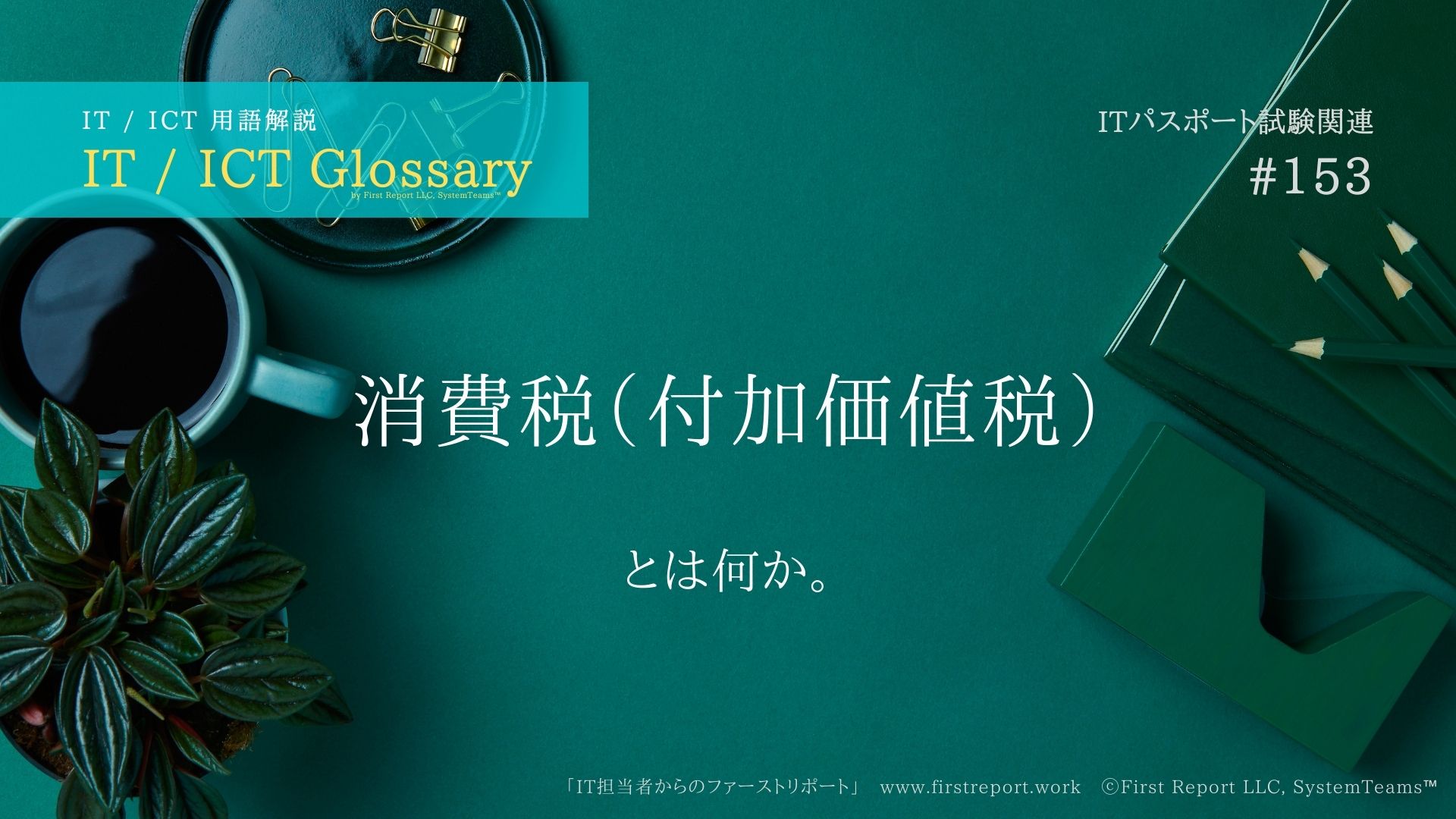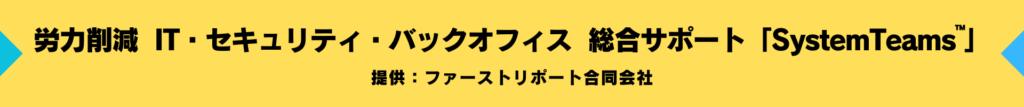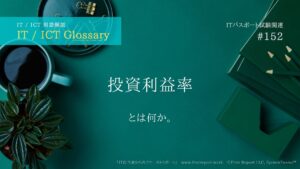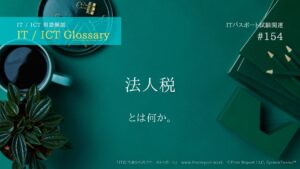「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「消費税(付加価値税)」です。
大まかに説明すると
消費税は、商品の購入といった「消費」にかかる間接税で、事業者が生み出す「付加価値」に課税されるため「付加価値税」とも呼ばれます。
会計処理上、事業者は売上で預かった「仮受消費税」(負債)から、仕入で支払った「仮払消費税」(資産)を差し引いた差額を国に納税します。
消費税ってどんな仕組みなのか
消費税(付加価値税)とは、商品を購入したり、サービスの提供を受けたりといった「消費」に対して課される税金のことです。
皆さんがお店で支払った消費税は、そのお店が皆さんに代わって国に納めています。
このように、税金を負担する人(消費者)と、税金を納める人(事業者)が異なる税金のことを「間接税」と呼びます。
付加価値税とは
日本の消費税は「付加価値税」という仕組みを採用しています。
付加価値とは、事業者が事業活動を通じて、新たに生み出した価値のことを指します。
少し難しく聞こえますが、パン屋さんを例に考えてみると簡単です。
製粉会社が、農家から小麦を仕入れ、加工して「小麦粉」という製品にします。
ここに価値が上乗せ(付加)されました。
パン屋さんが、その小麦粉やバターなどを仕入れて、こねて焼き、「パン」という商品にします。
ここでもさらに価値が付加されています。
私たち消費者は、最終的に完成したパンを購入します。
このように、商品が私たちの手元に届くまでには、いくつかの事業者が関わり、その都度「付加価値」が生まれています。
この各段階で生まれた付加価値に対して課税されるのが、付加価値税の基本的な考え方です。
そして、各事業者が納めた税金分は、最終的に商品の価格に上乗せされるため、結果として最終消費者がすべての税金分を負担する、という仕組みになっています。
会計と消費税
この消費税を会計上どのように扱っているのでしょうか。
事業者は、商品を売ったときにお客さんから消費税を「預かり」、逆に材料などを仕入れたときには消費税を「支払い」ます。
もし、預かった消費税をそのまま全額納めてしまうと、仕入れのときに支払った分と二重払いになってしまいますよね。
そこで、会計処理では次のように扱います。
仮受消費税(かりうけしょうひぜい)
売上があった際に、お客さんから預かった消費税のことです。
これは、いずれ国に納めるべきお金なので、会計上は「負債」として扱われます。
仮払消費税(かりばらいしょうひぜい)
仕入れなどで、他の事業者に支払った消費税のことです。
これは、最終的に納める税額から差し引くことができる(控除される)お金なので、会計上は「資産」として扱われます。
そして、決算の時期になると、企業は一定期間の「仮受消費税」の合計から「仮払消費税」の合計を差し引き、その差額を国に納税します。
つまり、「納税額=仮受消費税−仮払消費税」となります。
このように、消費税は企業の資金繰りや納税額に直接関わるため、会計・財務において非常に重要なのです。
まとめ
消費税は、商品の消費にかかる「間接税」である。
その仕組みは、事業者が生み出す「付加価値」に課税する「付加価値税」である。
企業会計では、「仮受消費税(負債)」と「仮払消費税(資産)」として処理し、その差額を納税する。
ITパスポート試験でも、こうした企業の基本的なお金の流れや、それに伴う会計のルールを理解しているかが問われます。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類1「企業活動」
3. 会計・財務
目標「企業活動や経営管理に関する、会計と財務の基本的な考え方を理解する。」
説明「企業活動や経営管理について、損益分岐点などの会計と財務に関する基本的な用語
の意味と考え方を理解し、身近な業務に活用する。」
(1) 会計と財務
・売上と利益の関係
③その他税関連
・身近な税に関する概要
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。