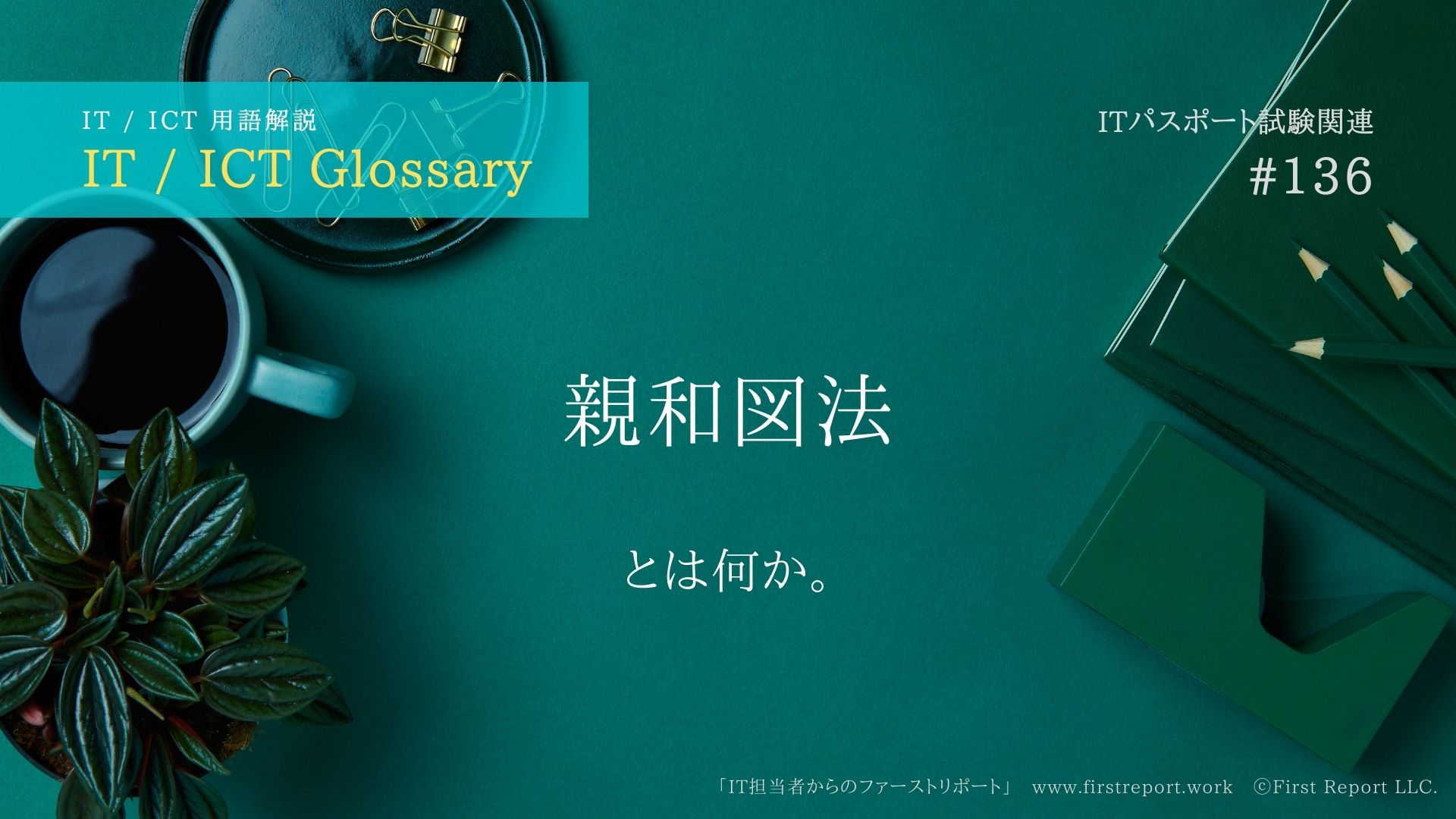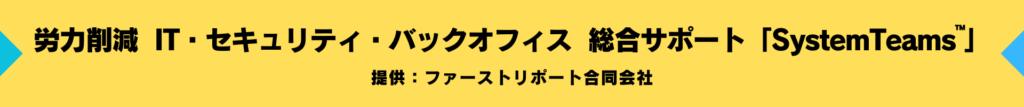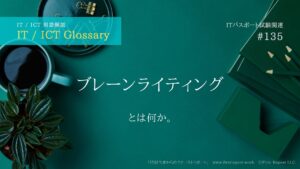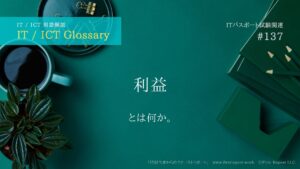「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「親和図法」です。
大まかに説明すると
親和図法は、言語データを集めて関連性の高いものをグループ化し、問題を明確化する手法です。
1967年に川喜多二郎氏が考案し、KJ法とも呼ばれます。
データをカードに記入し、親和性の高いカードをまとめて親和カードを作成します。
これにより、課題を整理し解決策を導けます。業種を問わず活用可能で、品質改善や顧客ニーズの明確化に役立ちます。
課題を整理し、社内コミュニケーションの促進にも効果があります。
親和図法とは
親和図法は、ある問題に対する事実や意見、発想を言語データ化して集め、これらから親和性の高いグループを作ることで問題を明確化するというものです。
問題点の解決方法を探るために利用される新QC7つ道具の一つとして知られています。
ここでいう親和性は、物事を組み合わせた際の相性の良さを意味します。
つまり、似たようなものを整理していくことにより、はっきりとしていない漠然とした課題や問題を明確にするために用いられるものです。
この親和図法は、文化人類学者として知られる故川喜多二郎氏により1967年に考案されました。
別名KJ法(川喜多二郎法)とも呼ばれています。
親和図法の具体的な進め方について
親和図法の具体的な進め方について解説していきます。
まず、問題に対する言語データを収集します。
できるだけ幅広いデータを集められるようにアンケートなどを用いて外部から収集するのもアリですし、社内で会議や対話する中で収集するのも良いでしょう。
また、業務において気づきがあれば随時メモをして残しておくのも問題や課題の収集に役立ちます。
次に、これらの収集した言語データを1つにつき1枚ずつカードにして書き起こしていきましょう。
書き起こした言語カードを関連しているカード同士を集め、親和性の高いグループをペアで作成して集めていきます。
その後、親和性に高いペアを作ったら、次に親和カードを作成します。
親和カードはそれぞれの言葉の意味が的確に表せる文章にすると良いでしょう。
こうして親和カードを作成していくと、課題や問題がより明確化され、結論を導き出すことができます。
どんな企業でも利用できる万能な手法
親和図法は、あらゆる業種で活用できる手法です。
製造業であれば品質改善に役立てることができ、商社においては新しい事業において商品やサービスを取り扱う際に活用することで、顧客ニーズを明確にしていくことができるでしょう。
まとめ
親和図法は、現在はっきりとしていない課題や問題を整理することによって、より明確化できる大変便利な解決策です。
また、親和図法を活用すると社内全体での対話も増え、コミュニケーションを活性化する機会にもなっています。
より良い事業を行っていくためにとても役立ちますので、ぜひ不明瞭な課題や問題に差しかかった時に活用できるので、ぜひ覚えておきましょう。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類1「企業活動」
2. 業務分析・データ利活用
目標「身近な業務を分析し、データの利活用によって問題を解決するための代表的な手法を理解し、活用する。業務を把握する際のビジュアル表現を理解し、活用する。」
説明「身近な業務を把握して分析する手法、代表的なビジュアル表現、データ利活用、OR(Operations Research)及びIE(Industrial Engineering)の手法を理解し、活用する。」
(5) 問題解決手法
・問題を解決するための基本的な手法
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。