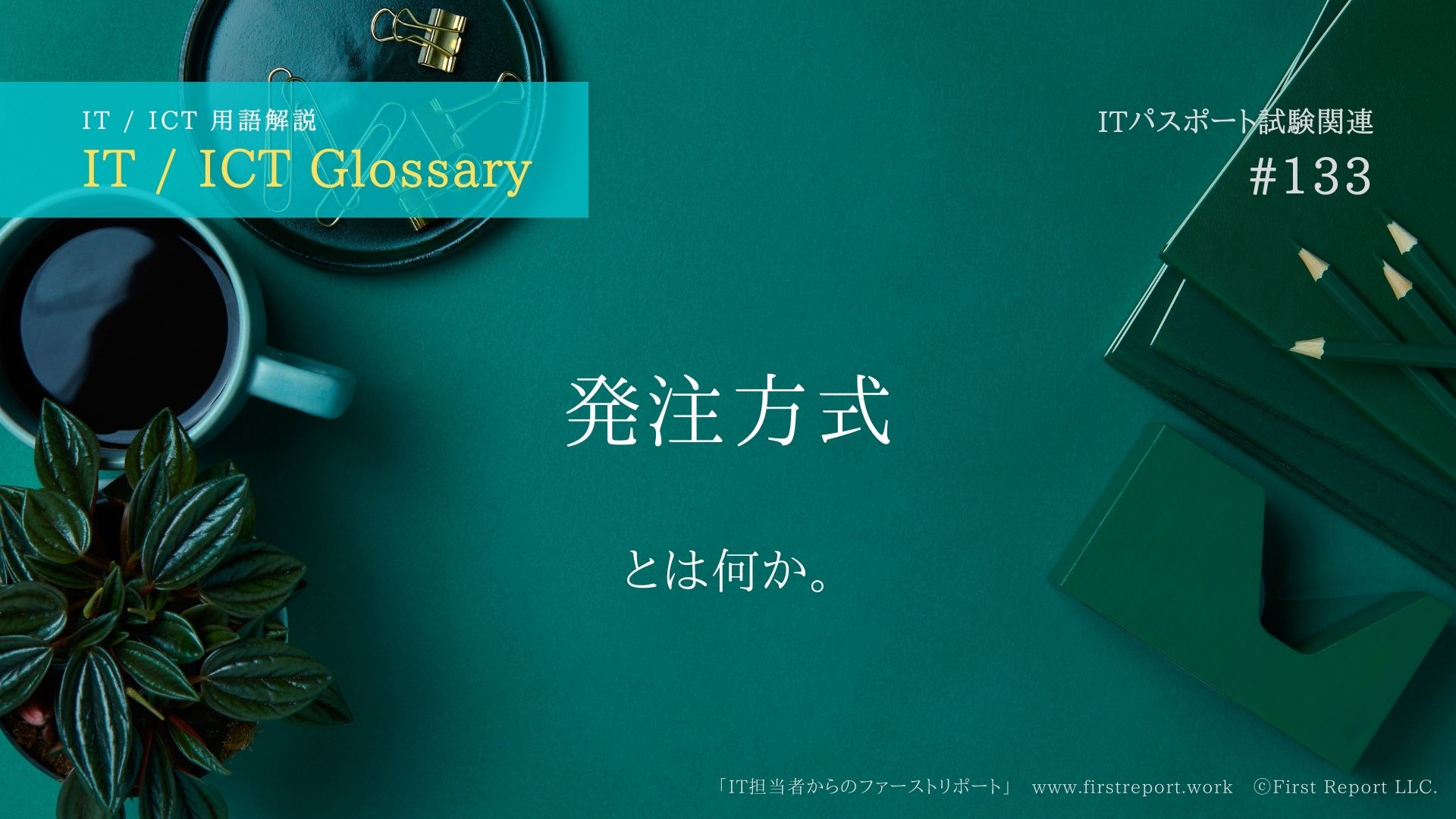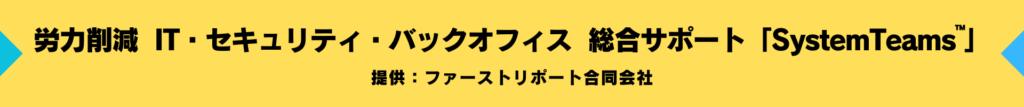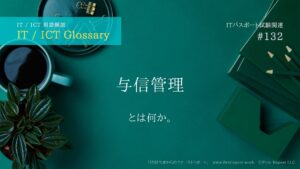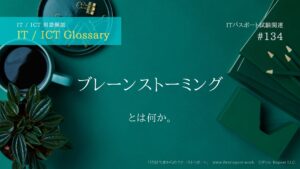「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「発注方式」です。
大まかに説明すると
発注方式には「定期発注方式」と「定量発注方式」があります。
定期発注方式は一定期間ごとに発注し、計画的な在庫管理が可能ですが、需要の急変には対応しにくいです。これは、需要が安定した商品に適しています。
定量発注方式は在庫が一定量まで減少したときに発注し、需要予測は不要ですが、在庫管理が重要です。これは、単価が低く劣化しにくい商品に適しています。
それぞれの方式には適した計算式があり、在庫管理の効率化に役立ちます。
発注方式とは
発注方式とは、在庫を適切に管理し、必要なタイミングで商品や資材を発注する方法です。
主に「定期発注方式」と「定量発注方式」があります。
定期発注方式とは
定期発注方式とは、一定期間ごとに発注を行う方式です。
発注のタイミングが固定されているので、計画的な在庫管理ができるのがメリットです。
発注のタイミングは一定ですが、発注の都度発注数量を決めることが必要になります。
発注量は、需要予測や在庫状況にもとづいて調整されます。
定期発注方式のメリットとデメリット
メリットとして、定期的に需要予測にもとづいて発注することで、在庫の過不足を防ぐことができ、安定供給ができます。
発注をするタイミングが決まっているので、計画的に発注ができ、発注コストや在庫保管コストの削減に役立ちます。
一方、急な需要増加に対する対応が難しい場合があるのがデメリットです。
需要予測が外れた場合や急な市場変動などがあった場合には、過剰在庫を抱えてしまうことや逆に在庫切れになって供給が追いつかず、売上チャンスを逃すリスクがあります。
定期発注方式に向いている商品と計算式
定期発注方式に向いているのは、需要が安定している商品や発注コストが高い商品です。
定期発注方式の計算方法は以下の通りです。
発注量=(発注間隔+調達期間)×1日の使用予定量+安全在庫-現在の在庫量-現在の発注残
定量発注方式とは
定量発注方式とは、在庫が一定の量まで減少した段階で、毎回決まった量を発注する方式です。
在庫数の検品や個数管理が大切になりますが、発注数は毎回一定の量を発注するので、需要予測などはしなくて済みます。
定量発注方式のメリットとデメリット
需要予測が不要で、難しいことを考えずに発注することができるのがメリットです。
デメリットとしては、日々検品を行い、在庫数を把握しておく必要があります。
タイミングは一定でないため、発注漏れをして在庫を切らすリスクがあるので注意が必要です。
現在では、POSシステム連動型のレジなどを用いることで、在庫が一定数に達すると発注をするアラートが出るような仕組みも開発されており、発注漏れのリスクを防げます。
発注した商品が届くまでに在庫が切れないよう、一定量の安全在庫を確保しておくことが必要です。
定量発注方式が向いている商品と計算式
単価が低い商品や安定した需要が見込めて入手しやすい商品、劣化しにくい商品、一度にまとまった量の補充がしやすく、まとめたほうが低コストで仕入れられる商品などは、定量発注方式に向いています。
たとえば、賞味期限が長く人気が高いお菓子や塩や砂糖など劣化しにくい調味料、長期保存ができてよく売れる洗剤などの日用品、腐らず、一気に売れることはなく安定的な需要が見込める文具などです。
定量発注方式の計算式は以下の通りです。
発注点 =(1日の在庫消費量 × 調達期間)+ 安全在庫
また、発注点とは、発注を行う在庫量のことを指します。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類1「企業活動」
2. 業務分析・データ利活用
目標「身近な業務を分析し、データの利活用によって問題を解決するための代表的な手法を理解し、活用する。業務を把握する際のビジュアル表現を理解し、活用する。」
説明「身近な業務を把握して分析する手法、代表的なビジュアル表現、データ利活用、OR(Operations Research)及びIE(Industrial Engineering)の手法を理解し、活用する。」
(4) 意思決定
・問題を解決するための効率的な意思決定
【活用例】
・与えられた条件の下での意思決定、在庫管理を題材にした業務把握
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。