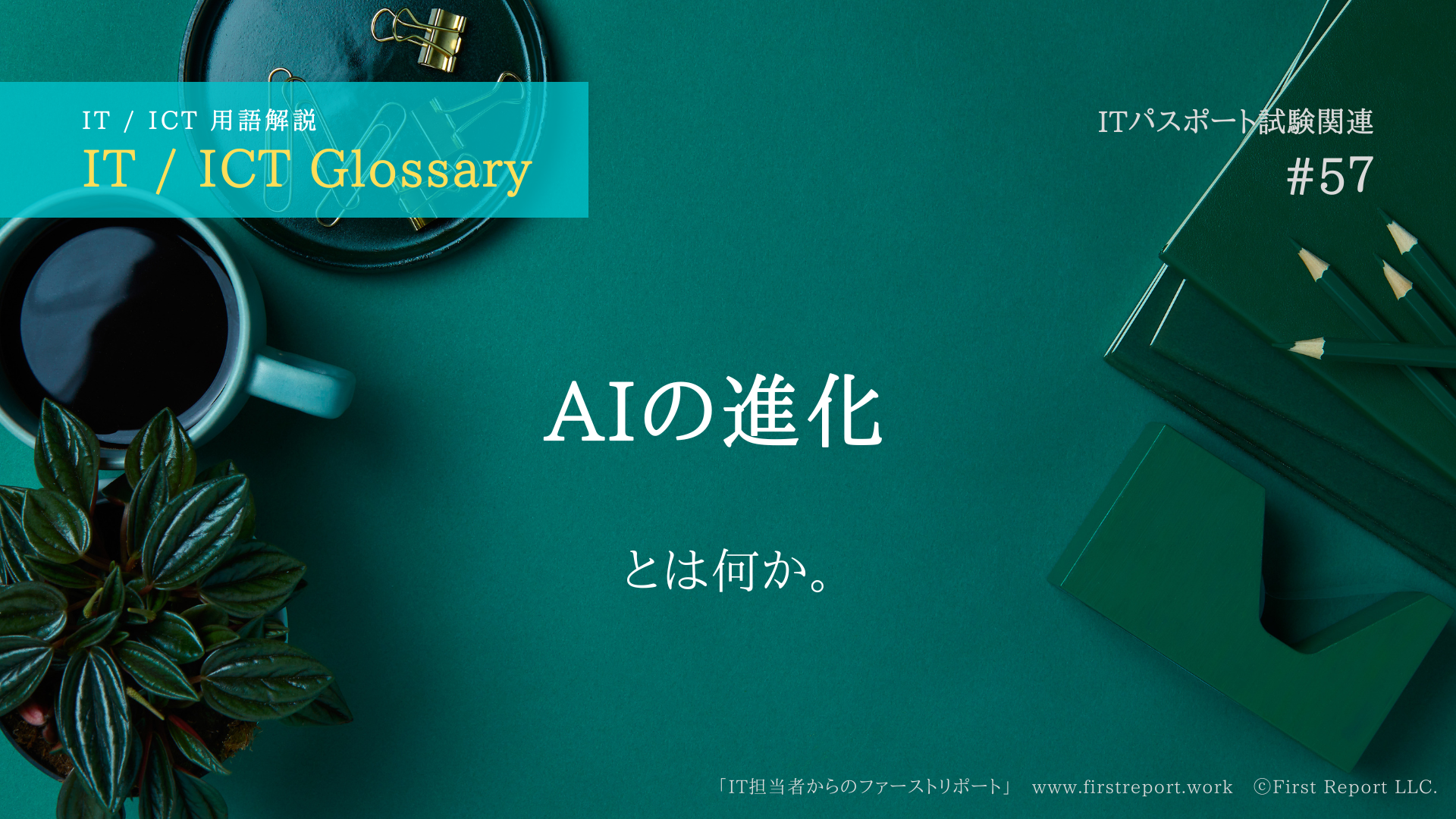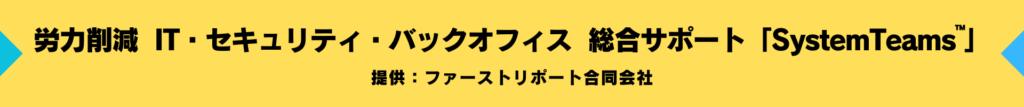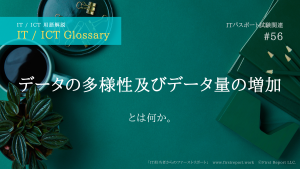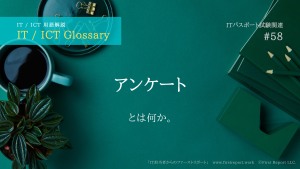「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「AIの進化」です。
大まかに説明すると
AIの進化の歴史は1950年代後半から始まり、第一次ブームでは推論や機械翻訳の技術が発展。しかし、現実課題解決には限界があり停滞。
第二次ブームではエキスパートプログラムが登場し、知識の与え方が進化。しかし、情報収集能力に限界があり、再び低迷。
第三次ブームは2000年代から続き、機械学習やディープラーニングが実用化。AIは大量のデータを自ら学び、自然なテキスト生成やクリエイティブな作品の制作も可能になりつつある。
AIの進化の歴史について
AIというと、近年になって誕生し、進化してきたように思われます。
実はAIの進化の歴史は1950年代後半から始まっています。
以下で第一次から第三次までの進化の歴史を見ていきましょう。
第一次AIブーム
第一次AIブームは1950年代後半~1960年代に起こったもので、コンピューターによる推論や探索ができるようになり、特定の問題に対して解を提示できるようになったことでブームが起こりました。
冷戦下のアメリカでは、自然言語処理による機械翻訳の技術開発が取り組まれました。
定理の証明といった単純な仮説を解くことはできても、現在のAIのように現実社会の課題を解くことはできなかったので、その後はAIの開発、進化が止まってしまいます。
第二次AIブーム
第二次AIブームはAI開発の冬の時代を経て、1980年代に入ってからです。
コンピューターが推論するために必要な情報を、コンピューターが認識できる形で記述した知識を与えることにより、AIが実用可能なレベルまで進化させることに成功しました。
プログラムに専門分野の知識を取り込ませて推論させることができるようになり、特定分野の専門家のように振る舞うエキスパートプログラムやシステムが生み出されていった時代です。
もっとも、コンピューターやシステムが自ら必要な情報を収集して蓄積することはできませんでした。
そのため、人が情報を集めて、コンピューターに理解できるようにプログラムを記述して、知識を与えなくてはなりません。
膨大なプログラムを記述していくには、膨大な作業量と時間がかかるため、その実用化はどうしても特定の領域に限られてしまいます。
そのため、再び限界に達し、1995年頃からAIの進化が再び低迷します。
第三次AIブーム
第三次AIブームは2000年代から再び起こり、現在まで絶え間なく続いています。
ビッグデータと呼ばれる大量のデータをAIが自ら集め、かつAIが自ら知識を学習していく機械学習が実用化されました。
知識を定義する要素をAIが自ら習得していく、深層学習や特徴表現学習とも呼ばれるディープラーニングもできるように進化しています。
さらに、テキスト生成に関するAI技術も生み出されました。
OpenAIが開発した大規模言語モデル(LLM)であるGPT-3やGPT-4、対話に特化したChatGPTを使うことで、人間に近い自然なテキストを生成することが期待されています。
また、AIによる、画像やイラストの自動生成技術も進化しており、AIが人間の美的感覚を学び、クリエイティブな作品を生み出すことができるようになっています。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類1「企業活動」
1.経営・組織論
目標「企業活動や経営管理に関する基本的な考え方を理解する。」
説明「担当業務を理解するために,企業の基本的な活動全体を理解する。担当業務の問題を把握し,解決するために必要なPDCA などの考え方や手法を理解する。」
(4) 社会における IT 利活用の動向
・② 企業活動及び社会生活におけるIT利活用の動向
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。