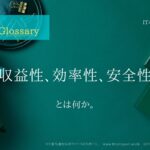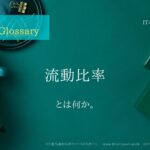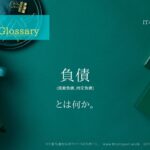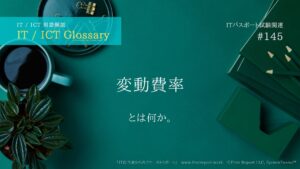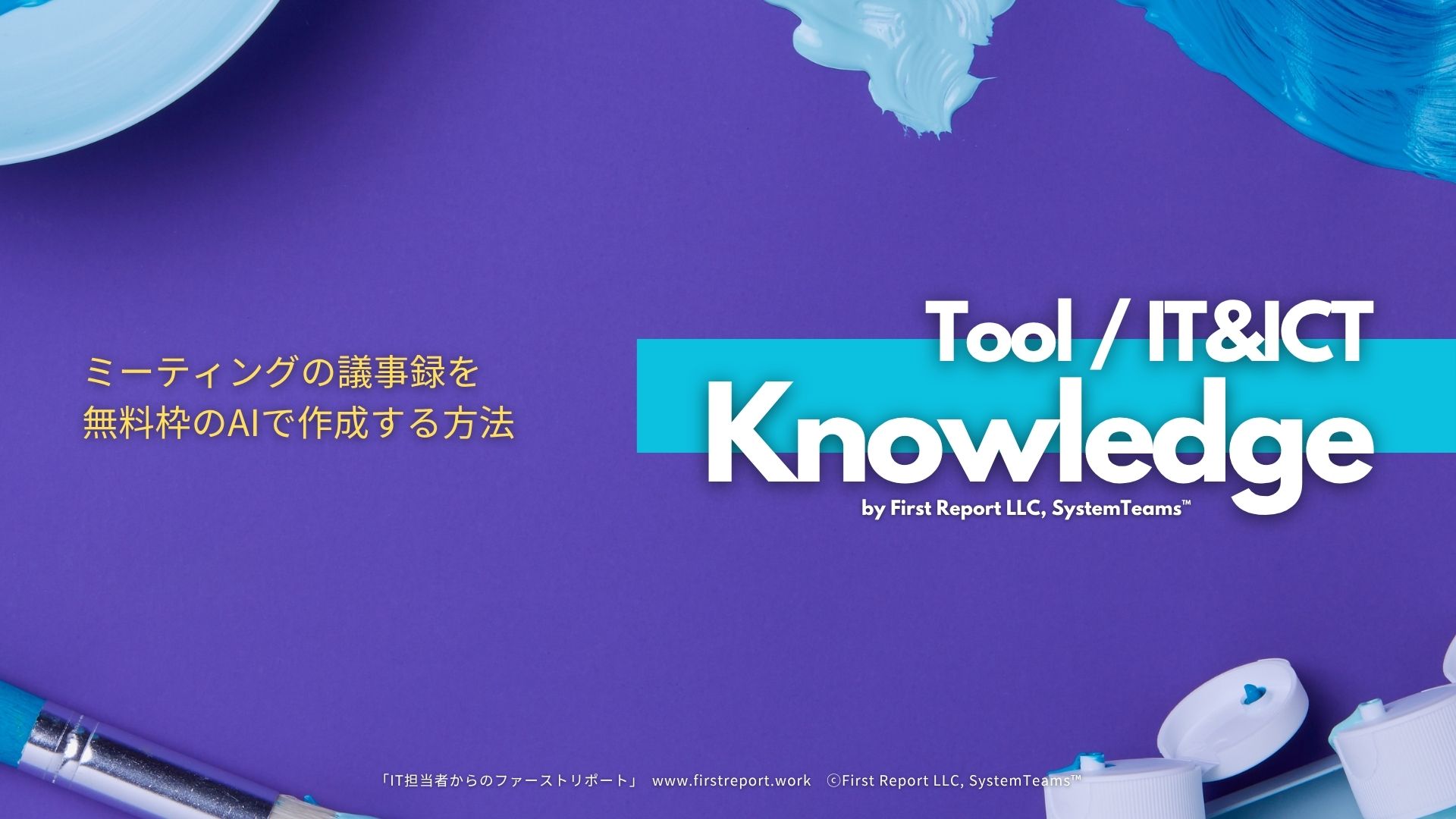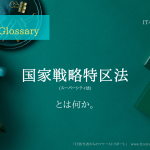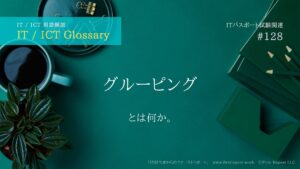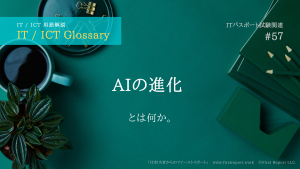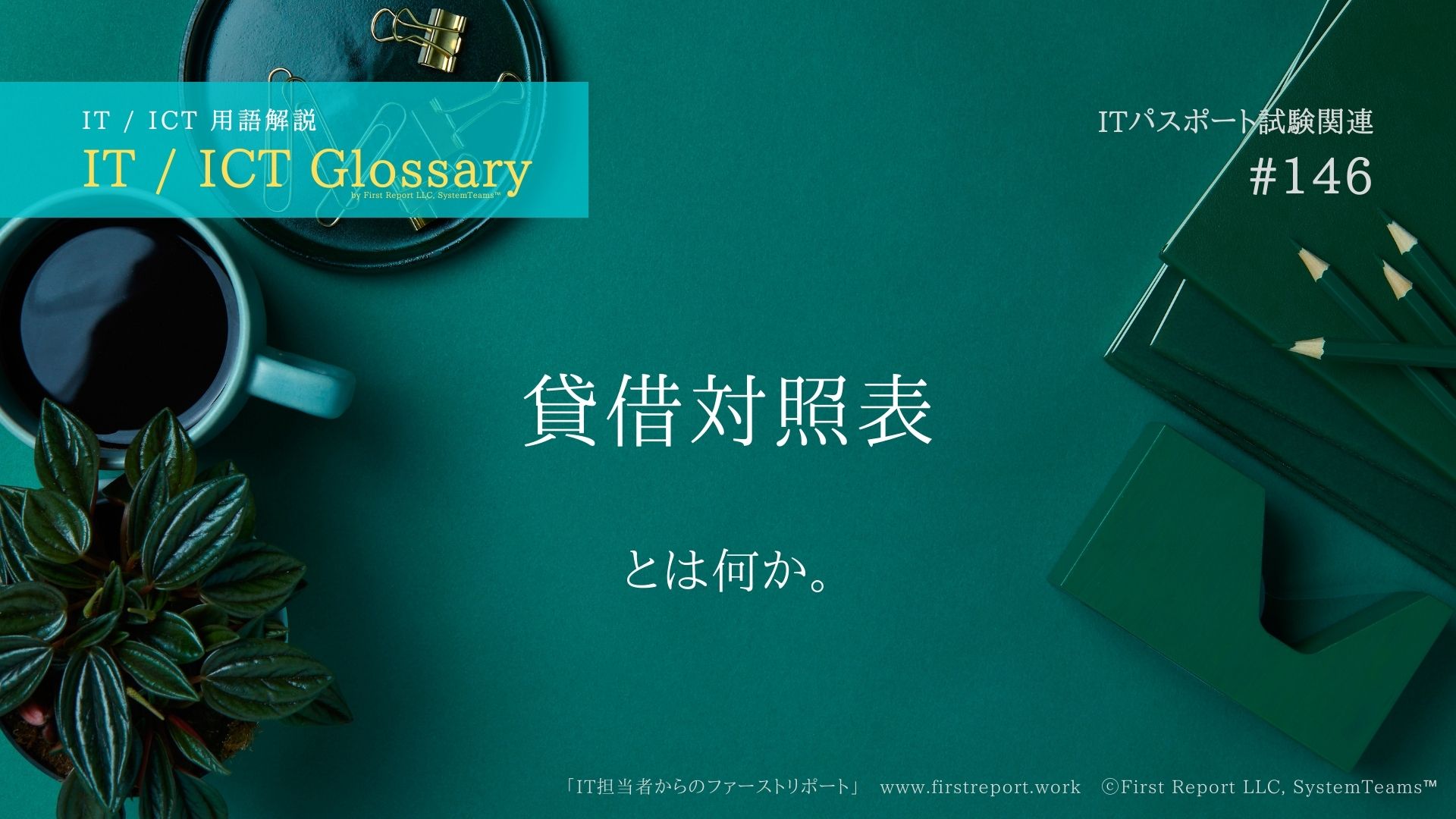
「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「貸借対照表」です。
目次
大まかに説明すると
貸借対照表は、企業の資産(財産)と負債(借金)の状況を示す書類で、バランスシートとも呼ばれます。
損益計算書、キャッシュフロー計算書と並ぶ財務三表の一つであり、企業の財政状態を把握する上で重要です。
左側に資産、右側に負債と純資産が記載され、資産は流動資産、固定資産、繰延資産に、負債は流動負債と固定負債に分類されます。
純資産は、資産から負債を差し引いたもので、自己資本とも呼ばれ、企業の安定性を示す指標となります。
貸借対照表とは
貸借対照表は、企業が保有している資産(財産)と負債(借金)の状況を記載した書類のことです。
読み方は、「たいしゃくたいしょうひょう」です。
英語では、「Balance sheet(バランスシート)」と表記します。
B/Sと省略されることもあります。
財務三表の一つ
この貸借対照表は、会社の財政状況や資金調達方法などを把握するうえで欠かせない重要な書類です。
損益計算書やキャッシュフロー計算書とあわせて、財務三表の一つにも数えられています。
貸借対照表と損益計算書は、決算時に必ず作成しなくてはなりません。
キャッシュフロー計算書の作成については、上場企業のみ義務付けられています。
貸借対照表の構成
貸借対照表は、左側と右側とに分かれた構成となっています。
向かって左側には資産、右側には負債と純資産が記載されています。
資産の部の記載項目
資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産の3つで構成されています。
流動資産は、貸借対照表日より1年以内に現金化される資産のことです。
現金預金、株式などの有価証券、受取手形、売掛金などが該当します。
固定資産は、長期にわたって保有することを前提とした資産のことです。
有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産などに分けられます。
固定資産に該当するのは、建物、土地、ソフトウェア、自動車、長期貸付金、有価証券などです。
繰延資産は、支出効果が1年以上になる資産のことです。
創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等、開発費などが該当します。
負債の部の記載項目
負債は、企業の負債のことです。
将来的に支出が発生するものを記載します。
負債は、流動負債と固定負債があります。
流動負債は、1年以内に支払う予定の負債のことです。
買掛金、支払手形、未払金、短期借入金、賞与引当金、預かり金、前受収益などが該当します。
固定負債は、年以上の長期間にわたり返済義務のある負債のことです。
長期借入金、社債、退職給付引当金などが該当します。
純資産の部の記載項目
純資産は、資産から負債を差し引いた額のことです。
社内に残った留保額のことを指しており、将来において返済義務が発生しません。
自己資本とも呼ばれています。
この純資産が多くなるほど、企業の経営が安定しているとみなされます。
純資産の部に記載するのは、資本金、資本剰余金、利益剰余金など株主資本です。
そのほかに、評価換算差額、新株予約権なども該当します。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類1「企業活動」
3. 会計・財務
目標「企業活動や経営管理に関する、会計と財務の基本的な考え方を理解する。」
説明「企業活動や経営管理について、損益分岐点などの会計と財務に関する基本的な用語
の意味と考え方を理解し、身近な業務に活用する。」
(1) 会計と財務
・売上と利益の関係
②財務諸表の種類と役割
・企業における損益計算書などの財務諸表や勘定科目などの種類と役割
【活用例】
基本的な財務諸表の読み方と財務指標を活用した分析
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。