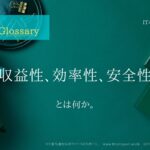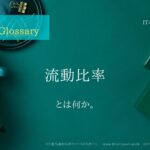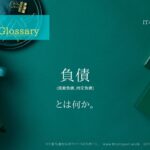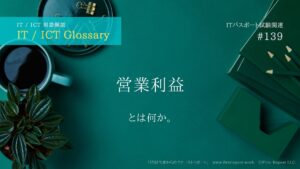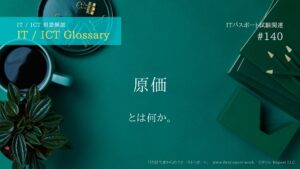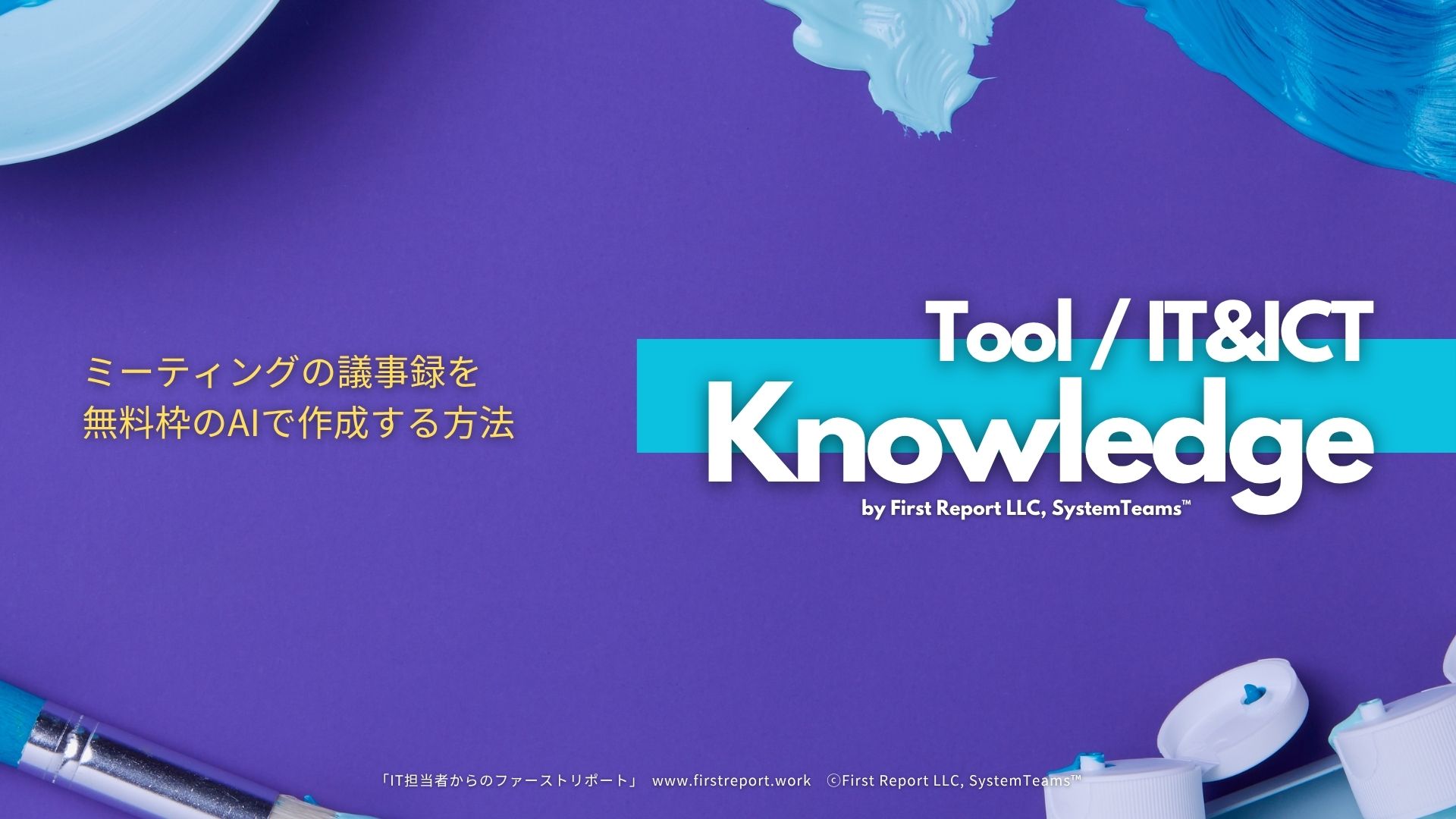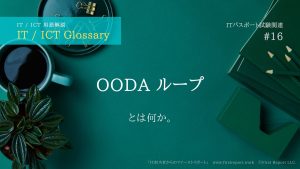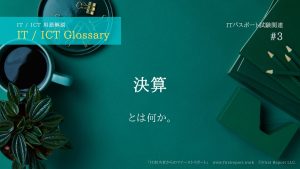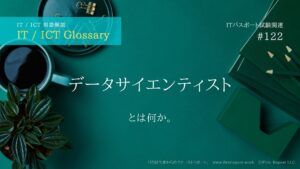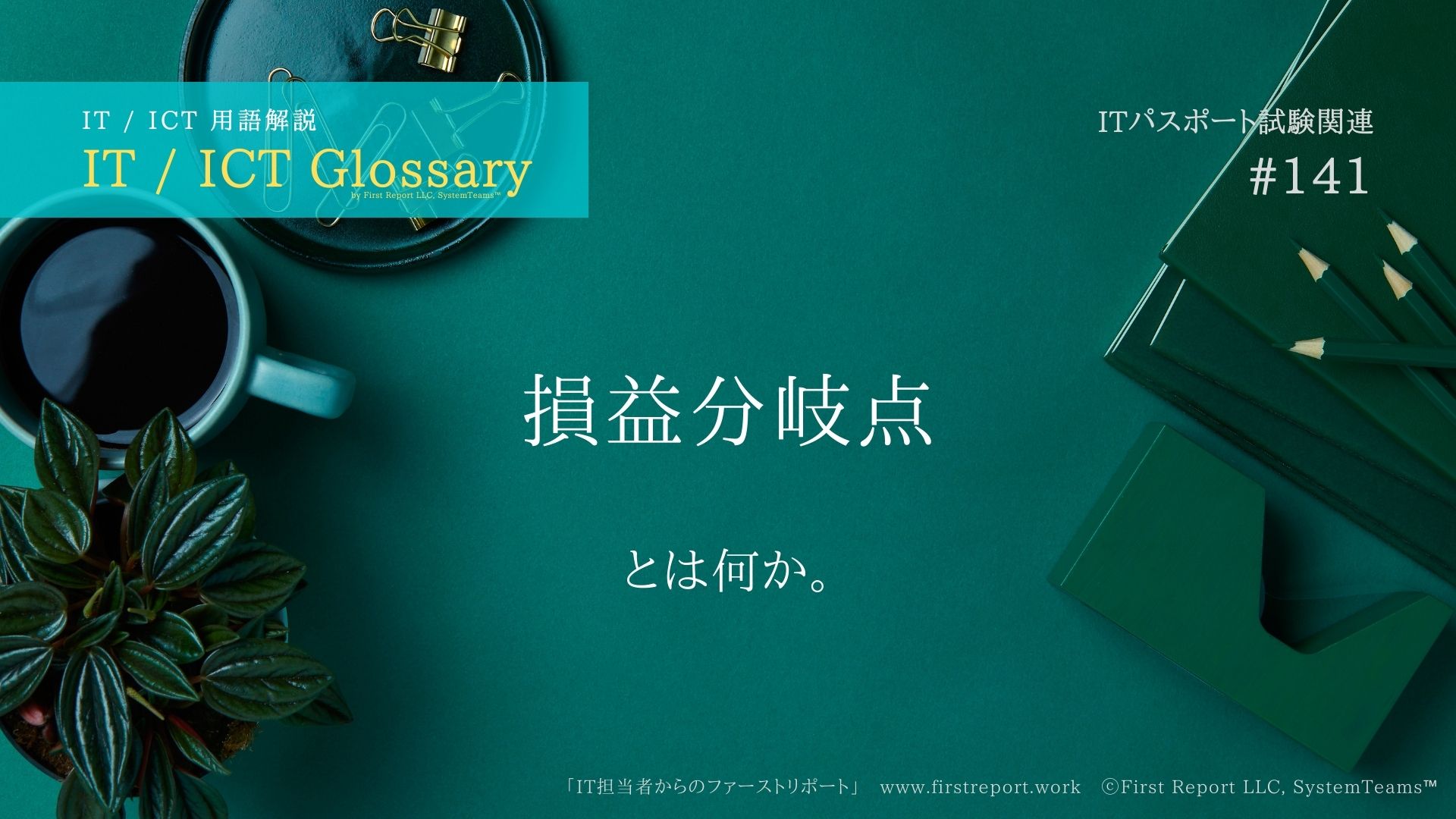
「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。
iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。
今回のキーワードは「損益分岐点」です。
目次
大まかに説明すると
損益分岐点は、売上高とコストが等しくなり損益がゼロになる売上高を指します。
これを上回れば黒字、下回れば赤字となるため、経営判断の重要な指標です。
損益分岐点は「固定費÷{1-(変動費÷売上高)}」で計算でき、コスト削減や価格見直しで改善可能です。
また、製品や事業ごとに分析すれば利益率の高い事業に集中し、経営効率を高めることができます。
損益分岐点の把握と活用が企業成長に役立ちます。
損益分岐点とは
損益分岐点とは、売上高とコストが等しくなる地点のことで、損益がプラスマイナスゼロになる売上高を示します。
売上高が損益分岐点を上回れば、利益が出て黒字になりますが、売上高が損益分岐点を下回ると損失が出て赤字になります。
そのため、健全な企業経営をしていくうえで、損益分岐点は重要な指標です。
損益分岐点の求め方
損益分岐点は以下の計算式で求めることができます。
損益分岐点=固定費÷{1-(変動費÷売上高)}
固定費とは、売上高の増減に関係なく、常に発生するコストのことです。
たとえば、賃料やリース料、光熱費や役員報酬などの人件費も含まれます。
これに対して、変動費は売上に応じて変動する費用です。
たとえば、原材料費や運送費、外注費、販売手数料などが該当します。
損益分岐点と経営判断
損益分岐点は企業が赤字になるのか、黒字になるのかの分岐点になりますので、とても重要な指標です。
経営を安定化させるには、損益分岐点となる売上高を把握する必要がありますし、利益を上げて成長していくには、損益分岐点を超えて売上を上げていかなくてはなりません。
単に売上を伸ばすのではなく、たとえばコストカットなど費用の見直しを図ることや値上げするなど、価格を上げることも検討が必要です。
損益分岐点を導き出して有効活用しよう
損益分岐点は、単に計算してプラスマイナスゼロの地点を確認するだけでなく、分析を行い、今後の経営判断に有効活用していくことが求められます。
たとえば、以下のような経営判断の指標です。
販売価格の見直しや適正化
固定費や変動費などの原価をしっかりと把握したうえで、市場のニーズや消費者のニーズなどを踏まえて適正価格を設定することが大切です。
損益分岐点は、利益が出せるかの重要なポイントです。
製品や商品、サービスや事業ごとに分析する
損益分岐点は、販売する製品やサービス全体で見るだけでなく、個々の製品やサービスごとに計算することや一方で事業全体での分析も可能です。
企業では、複数の製品やサービス、事業を運営していることが多いため、損益分岐点を比較、分析することで、どの製品やサービス、どの事業の利益率が高いのか、どれが損失を出しがちなのかチェックすることができます。
場合によっては、稼げていない製品やサービスを停止することや利益が低迷している事業から撤退し、稼げる製品やサービス、事業に必要な人材やコストを集中させることで、企業の利益向上や成長につなげることができます。
本キーワードの関連情報
今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。
試験のご参考にもなれば幸いです。
カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類1「企業活動」
3. 会計・財務
目標「企業活動や経営管理に関する、会計と財務の基本的な考え方を理解する。」
説明「企業活動や経営管理について、損益分岐点などの会計と財務に関する基本的な用語
の意味と考え方を理解し、身近な業務に活用する。」
(1) 会計と財務
・売上と利益の関係
① 売上と利益の関係
・用語と考え方
【活用例】
損益分岐点や利益率などの簡単な計算
参考・引用元資料
【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。